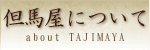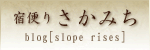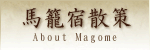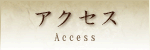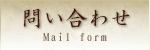馬籠宿散策


馬籠宿散策
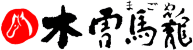
中山道六十九次のうち木曽路には十一の宿場がおかれていました。
馬籠宿は板橋から数えて四十三番目となります。江戸(東京)からの距離は約八十三里(約333km)となります。宿場は山の尾根に沿った急斜面にあり、通りに面した建物は石垣をくんで建てられています。周りの自然・山々の四季の変化もお勧めです。坂の町・馬籠宿の石畳を歩いてみて下さい。
| 【馬籠宿】宿場 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
・中山道は江戸日本橋を起点とし京都まで約530kmの道路で、ここには69箇所の宿場がおかれていた。
・東海道の504kmに比べ遠回りではあったが、東海道には大井川の川止めをはじめ海の旅や川越などの危険が伴った。 ・中山道69宿のうち木曽には11の宿場があり、馬籠宿は板橋を1番目とすると43番目になり、江戸からの距離は332kmになる。 ・道路が南北に貫通しているが急な山の尾根に沿っているので、急斜面で、その両側に石垣を築いては屋敷を造る「坂のある宿場」である。 ・山の尾根のため水に恵まれておらず、火災が多いのが特徴である。 【消失棟数】
|
|||||||||||||
| 【今に残る宿場の面影】 | |||||||||||||
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
・一里塚・・・旅の行程の目安として4kmごとに道路の脇に土を盛って塚を築いた物で馬籠宿と落合宿の境に今も残っている。
・桝形・・・・宿場の入り口に道路を直角に2度曲げた物、軍事的な目的を以て作られた。 ・高札場・・村人や旅人に法令を徹底させる手段として設けられたもので、宿場の入り口にある(復元) ・本陣、脇本陣・・公儀の旅に備え宿泊、休憩のための施設として宿場には必ず設けられた(遺構) |
|||||||||||||
| 【明治維新以降の馬籠宿】 | |||||||||||||
|
・明治新政府の発足により宿場の機能は相次いで廃止された。
・1882年(明治25年)中山道に変わって木曽川沿いに国道が開設され、さらに1912年(明治45年)国鉄中央線が全線開通したことにより、馬籠、妻籠は全く人通りが絶え、両村は陸の孤島化し、村の経済は急速に寂れていった |
|||||||||||||
| 中山道と馬籠宿 | |||||||||||||
| 【街道の成立】 | |||||||||||||
|
慶長5年(1600)の関ケ原の合戦で勝利をおさめた徳川家康は、翌年東海道の整備を手始めに順次交通網の整備に着手し、幕府が管轄する道路を定めこれらの道路には多くの宿駅を定めた。
中山道は江戸日本橋を起点とし京都まで132里(約530km)の道程で、ここには69の宿場が設けられていた。本州の中部山岳地帯を縦断し、木曽を通っていたことから別名を「木曽路」とも「木曽街道」とも呼ばれていた。 始めは《中仙道》 と書かれていたが、享保元年(1716)に、「東の海沿いの道を東海道というように、本州の中央を通る道だから《中山道》と書き改めるべきである」として、以後《中山道》と書かれるようになった。しかし《なかせんどう》と読まれた。 中山道は東海道と共に江戸と京都を結ぶ大動脈であった。東海道の126里・53宿に比べて遠回りではあったが、東海道は大井川の川留めで旅の行く手を遮られたり、桑名一宮間の船旅で海難の危険が伴ったのに対し、中山道の旅にはこうした惧れがなかったことから、京都から江戸に向かう姫君たちはほとんど中山道を選んだ。しかし中山道も決して安全な道ばかりではなく、とりわけ馬籠宿と落合宿の間にある十曲峠は険しさで旅人をはばみ、木曽の桟(かけはし)は危険な箇所として恐れられていた。 かけはしや 命をからむ つたかづら 芭蕉 |
|||||||||||||
| 【馬籠宿】 | |||||||||||||
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
中山道69宿のうち木曾谷には11の宿場が置かれており、馬籠宿は板橋を1番目とすると43番目になる。江戸からの距離は83里(333km)余りとなる。
街道が山の尾根に沿った急斜面を通っており、その両側に石垣を築いては屋敷を造っていることから「坂のある宿場」が特徴となっている |
|||||||||||||
| 【一里塚】 | |||||||||||||
|
幕府が街道を整備するとき、一里(4km)ごとに道の両側に土を盛った塚を築いて旅の行程や駄賃・運賃の目安とした。塚の上には榎や松の木を植えてその目印にした。
現在馬籠宿と落合宿の境にその1基が残っている。中山道では唯一の遺跡である。 |
|||||||||||||
| 【桝形】ますがた | |||||||||||||
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
馬籠の南側の入り口に道路を直角に二度折り曲げた所がある。この部分の道路の山手側は切り土になっていて、城郭建築の桝形に摸して石垣を築いてあったことから、ここを
「桝形」といった。本来宿場が軍事的な目的をもって作られていたことを示している。 |
|||||||||||||
| 【高札場】こうさつば | |||||||||||||
|
宿や村の庶民に法令を徹底させる手段として高札場が設けられていた。高札場の管理は厳重で、古くなって墨文字が薄くて墨入れを必要とするようなときでも藩の指示を待たねばならなかった。
現在馬籠では当時の場所に忠実に復元してあるが、その内容は正徳元年(1711)の記録のものである。 |
|||||||||||||
| 【本陣・脇本陣】 | |||||||||||||
|
本陣・脇本陣は共に公儀宿泊休憩のための施設として宿場には必ず設けなければならなかった。本陣は高貴な人の宿泊に備え、広大な邸宅と多くの使用人を常に抱えていなければならず、このためかなりの財力を必要とした。多くは世襲制で一種の家格となっていた。本陣だけでは受け入れ収容に支障があるので脇本陣を置いた。脇本陣は建物や規模などは本陣に準じており本陣同様世襲になっていた。
本陣に休泊できるものは、勅使、院使、宮、門跡、公家、大名、旗本などで一般のものは原則として利用できなかった。本陣・脇本陣ともに貴賓客が使用する専用の部屋が設けられ、ここを「上段の間」といって他の部屋より床が15〜18cm高く作られていた。また専用の風呂場と便所があり、これらの施設は家族といえども使用が禁じられていた。 |
|||||||||||||
| 大名の休泊 | |||||||||||||
|
中山道の通行はなかなか頻繁で参勤交代の西国大名34家の指定路であり、尾州侯の参府は中山道であった。このほか大阪二条城番・日光例幣使などは片道は必ず中山道を利用した。
皇女、親王家・姫宮の降嫁の節の道筋は殆ど中山道を利用しており、このため中山道は姫街道などともいった。 |
|||||||||||||
| 旅籠 | |||||||||||||
|
本陣や脇本陣が高貴な人々の宿泊に備えるものであれば、一般の旅人の利用する宿泊施設に旅籠・商人宿があり、さらに下級な施設に木賃宿や馬宿があった。
旅寵は食事を提供してくれる宿屋であり、木賃宿は食事の提供はなく泊めるだけの宿である。馬籠宿には8軒ほどの旅籠があった。 |
|||||||||||||
| 馬宿 | |||||||||||||
|
馬宿は荷物運搬を業とする駄賃稼ぎの人々を相手とする旅舎で、牛馬と牛馬引きの人を同時に宿泊させた。宿には牛馬を係留する厩があり牛馬には飼料を与えた。宿泊料は木賃程度で旅舎としては粗末な部位に属した。宿場の入り口付近に2軒あったことが記録に残る。
|
|||||||||||||
| 木曽義仲の妹、菊姫にまつわる話 | |||||||||||||
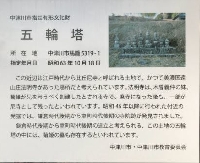  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
|
|||||||||||||
| 【尼寺を設立】 | |||||||||||||
|
冶承4年〈1180)に平家追討の兵を挙げ朝日将軍とまでいわれた木曽義仲は僅か4年にして元暦元年1月、粟津原で悲惨な最期を遂げた。義仲に宮菊という1歳違いの異母妹がいた。鎌倉幕府の日記ともいうべき「吾妻鏡」4、文治元年(1185)の条によれば、頼朝の妻の政子は宮菊を「やしない子(養女)」にして慈しんでいた。都に居た菊姫は将軍の息女ということで威光があったため、周囲にいたよからぬ者たちが、菊姫の名前を騙って役に立たぬ古文書をあげたり、不知行の荘園を寄付したり、また菊の使いだといって官位が高く権勢のある家柄の荘園の年貢を横取りしたりした。これらのことが鎌倉の頼朝の耳に入り、頼朝は菊姫を捕らえて鎌倉に連れてくるように命じた。
鎌倉に捕らえられた菊姫は、横領のことや悪事の数々は、悪巧みをした人々が自分の名前を騙ってしたことで自分は一切知らないと弁明した。政子のとりなしもあって頼朝は、兄義仲は朝敵として討ったが菊姫に罪はないとして、その境遇に同情し『美濃国遠山の荘の一村』を与え、義仲恩顧の御家人である小諸太郎光兼らに命じて菊姫の面倒をみさせた。遠山の荘の一村とは馬籠のことだという説が定着している。 |
|||||||||||||
| 【墨書き大般若経】 | |||||||||||||
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
永昌寺に墨書きの大般若経二冊が伝えられている。いつどこからきたものか不明だが、その経文の奥書には「建保三年五月一二日校始之…」とあり、さらに別書きで「美濃州遠山庄馬籠村法明寺常住」と記されている。建保三年(一二一五)は鎌倉初期のころで、この二つが書かれた時代が同じ時期なら、馬籠の地名がすでにこのころから使われていたことを立証するものであり、菊姫の手によって書かれたものではという推論もある
|
|||||||||||||
| 【阿弥陀如来座像】 | |||||||||||||
|
永昌寺の本堂横の観音堂には一体の木造の阿弥陀如来像が安置してある。桧の一木造りで平安末期の作である。
この像は本来永昌寺のものではなかった。土地の古老の話によれば、永昌寺から少し離れた原野の中の小堂に祀られていたが、いつ、だれの手によって祀られたものか知る人も無く守る人も無いまま荒れ果てていた。あまりの痛ましさに見かねた村人たちが、明治の初め頃永昌寺に運んだという。然し永昌寺でも素性の判らぬ仏様ということで放置していたところ、昭和三○年頃彫刻家の石井鶴三氏がこの仏像のあまりにも見事なことに驚嘆し、寺に保存を進言した。そこで村人は昭和四五年になって堂宇を寄進してここに安置するようになった。 鎌倉末期の作であること、そしてその作風の見事なことから、いずれ都の仏師によって作られた仏像であろうと推定され、菊姫が鎌倉から運んで釆たものではなかろうかなどとも言われている。さきの大般若経とともに現在山口村(現中津川市)の文化財に指定されている。 なおこの阿弥陀堂には阿弥陀仏に並んで円空の作になる「聖観音立像」一体が祀られており、これも山口村(現中津川市)の文化財に指定されている |
|||||||||||||
| 馬籠の路傍に残る文学碑 | |||||||||||||
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
馬籠を抜ける一筋の道は中山道。大名が通り幾多の旅人を迎えたのは江戸の昔。その街道筋には歴史を語る文学碑が随所に建っている。
馬籠峠の正岡子規の句碑 妻籠から馬籠に向かって峠を上り切ったところの茶屋の脇に”白雲や青葉若葉の三十里 子規”の句碑がある。句の出典は子規の紀行文「かけはしの記」で、句の傍らには馬籠と妻籠までの道程が併記されている |
|||||||||||||
| 【馬籠峠の道しるべの碑】 | |||||||||||||
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
所在地 馬籠峠 中山道の路傍
昭和31年、南木曽町の有志によって建立された。 碑にある子規の俳句は「かけはしの記」から採られており、この句の前に次の文が書かれている。 ・・・・・馬籠峠の麓に来る。馬を尋ねれども居らず。詮方なければ草鞋はき直して下り来る人に里数を聞きながら 上りつめたり。此山を越ゆれば木曽30里の峡中を出づるとなん聞くにしばし越し方のみ見返りてなつかしき心地す。 白雲や青葉若葉の三十里 |
|||||||||||||
| 【十辺舎一九の狂歌碑】 | |||||||||||||
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
峠の集落を抜けたあたりの路傍に江戸時代の滑稽本の作者・十返舎一九の狂歌「渋皮の剥(む)けし女は見えねども 栗のこはめしここの名物」 十返舎一九の碑が目に入る。ここは古くから栗こわめしを名物にしていた所で、文化8年(1811)に十返舎一九は中仙道を旅して「木曽街道膝栗毛」を書いた。
十返舎一九(1765−1831)は駿府の生まれ。小田切土佐守に仕えたが、武士を辞めてからは文筆の道に入り享和2年(1802)に滑稽本《東海道膝栗毛》を出すに及んで文壇的な地位を確立した。執筆の材料集めに各地を旅行したが、狂歌が巧みで、書や絵にも詳しかった。晩年は酒のため手足の自由を失い、生活も苦しく神田紺屋町の自宅で67才の生涯を閉じた。 |
|||||||||||||
| 【山口誓子の句碑】 | |||||||||||||
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
馬籠のほば中央にある馬籠脇本陣史料館の前に、山口誓子の“荷道の坂に熟柿灯を点す 誓子”の句碑がある。誓子は生前馬籠をこよなく愛し、しばしば奥さんの波津女さんと共に馬籠を来訪し多くの作品を発表した。
この碑は、昭和57年12月、明治書院から発刊の「山口誓子全集」の完結を記念して流域俳句会によって建立されたもので、文字は山口誓子自身の筆になるもの。 |
|||||||||||||
| 【島崎藤村の「太陽のことば」の碑】 | |||||||||||||
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
藤村記念館第二文庫の正面左横に高さ106センチ、幅87センチの自然石にはめ込まれた銅版に陰刻で「誰でもが太陽であり得る。わたしたちの急務はただただ眼の前の太陽を追いかけることではなくて、自分等の内部に高く太陽を掲げることだ 島崎藤村」と藤村自筆の碑がある。この文の出典は、大正14年1月28日付けの朝日新聞に掲載の「春を待ちつつ」から抜粋されたものである
|
|||||||||||||
| 【島崎藤村の「母を葬るの歌」の碑】 | |||||||||||||
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
永昌寺横の小さな公園の一角に、藤村の詩「母を葬るのうた」(若菜集)が建てられている。
藤村の母、縫子は明治29年(1896)10月25日、東京で居住中の長男秀雄のもとで死去した。当時東北学院の教師だった藤村は遺骨を抱いて埋葬のため帰省。「母を葬るの歌」は明治30年8月発行の処女詩集「若菜集」に収録された |
|||||||||||||
| 【正岡子規の句碑】 | |||||||||||||
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
所在地 新茶屋 中山道の路傍
「桑の実の 木曽路出づれば 穂麦かな 」子規 正岡子規(1867-1902)は明治期の俳人・歌人。本名は常規、松山の出身。明治26年東京大学を中退後俳句革新を唱え、さらに「歌よみに与ふる書」で万葉を理想とする短歌革新を唱えた。 「かけはしの記」には、この句の前に「馬籠下れば山間の田野照稍々開きて麦の穂已に黄なり。岐蘇の峡中は寸地の隙あらばここに桑を植え一軒の家あらば必ず蚕を飼うを常とせしかば、今ここに至りて世界を別にするの感あり。」と述べている。 この碑は昭和54年9月、馬籠観光協会によって建立された |
|||||||||||||
| 【島崎藤村の「是より北木曽路」】 | |||||||||||||
  クリックすると大きな画像が見られます. クリックすると大きな画像が見られます.
中山道の長野県と岐阜県(現在は岐阜県)を接する路傍に島崎藤村の筆で「是より北木曽路 藤村老人」と書かれた碑がある。昭和32年11月17日に藤村記念堂落成10周年記念事業として建てられた。
藤村がこの碑文を書いたのは昭和15年(1940)のことで、このころ藤村は3年越しの病気の保養に努めていたころであり、この年の2月には《巡禮》を、11月には《力餅》など藤村童話叢書を刊行している |
|||||||||||||