| 【馬籠に伝わる方言】〜幾つわかるでしょうか? |
|---|
|
【現在、若い人はあまり使わなくなった方言ですが、伝承のつもりで残しておきます】
- 馬籠 ふるさとのことば - |
- 馬籠のことば
- 馬籠のことばには一部の例外を除いて「男ことば・女ことば」の区別がない。男も女もほぼ同じことば遣いで話す。ことばに関する限り神坂(みさか:この地方名)は男女同権だった。
女性の場合、名詞の上に「お」をつける丁寧ことばの殆どないのも特徴である。日常会話で両親を「オトウ」「オカア」、食事で「オサイ」、「オカズ」、「オシイ(汁)」などに「オ」がつくのは例外である。
しかし宗教的な事柄には「オ」をつけた丁寧語が使われていた。たとえば、「お寺」、「お宮」、「お墓」、「お薬師」、「お祭り」、「お日待ち」など。
- 日常のことばづかい
- �
 e 自分のことを男女共にオレ。オラホは自分の家で、オラヤタは自分たち。オトウは父、オカアは母。ジジは祖父で、ババは祖母。 e 自分のことを男女共にオレ。オラホは自分の家で、オラヤタは自分たち。オトウは父、オカアは母。ジジは祖父で、ババは祖母。
ニイマは兄で、ネエマは姉。オッサマは伯叔父で、オバサマは伯叔母。 ネンネは赤ん坊。 対人称 多くの農家が小作であった関係から、身分関係をかなり強く意
識していた。そのため相手によりことばづかいが幾通りにも変わってゆ く。最上級の家格の人には名前に様を付けて呼ぶ「様付き」である。様 付きで呼ばれるのは旦那衆といわれた人々である。
様付き呼ばれる家格の家へ来た嫁に対しては、名前の代わりに「ネエサマ」と呼ぶ。ネエサマは「姉様」の意で、主婦に対する最上格の表現である。ネエサマが幾軒もあるので、屋号をつけて「○○屋のネエサマ」といって区別する。ネエサマと呼ばれた人も、やがて次の世代に嫁がくると「様付け」に格上げされる。だだし自分のことをネエサマとはいわない。
様付けの次のランクの人々に対しては、サマのサを取り去って名前の次に「マ」を付けて呼ぶ。兄サマを「ニイマ」、姉サマを「ネエマ」、は一般的な呼び方だが、芳江がヨシマ、明をアキマと呼ぶ。
その次のランクが「サ」を付けて呼ばれる階級で「九蔵サ」・「お民サ」など、最も広くそして一般的に使われているものである。 親が子供を呼ぶときや男の子同士が仲間を呼ぶときは名前の呼び捨てであった。
名前を呼ぶとき、長い名前だと下を適当にチョン切って、下に「サ」を付けた。為之助が「タメノサ」、銀三郎が「ギンザサ」など。 名前の下に「コウ」をつけて呼ぶことがある。コウは公で、敬称ではなくて愛称に類するもので、男に限られていた。
「サ」ランクの人が年老いてくるといつの間にか「サ」が「ジイ」「バア」に変わり、「ワスケジイ」・「オトシバア」と呼ばれるようになる。親しみを籠めた呼び方である。
肉親でなくても、尊敬や親しみに意味で、名前にニイ(兄)・ネエ(姉)を付け、「キサオニイ」・「サダネエ」などと呼ぶ。こう呼ばれた人は終生「ニイ」「ネエ」である。峠地区にこの呼びかたが多く見られる。 - 普段語とよそ行き語
- 親しい者同士や、親が子供に向かっては、相手のことを「ワレ」と呼ぶ。少し改まった場合は「オマエ」。目上の人や家格の高い人に対しては、たとえ相手が子供であっても「オマエサマ」という。あなたの家は「ワイラホウ」。丁寧語になると「オマエタホウ」でさらに丁寧に言うときは「オマエサマントコ」となる。
日常会話は命令調で、「オケヨ」、「コイヨ」、「クエヨ」で、語尾の「ヨ」に力が入る。これが丁寧語になると「オカンショ」、「コンショ」、「クワンショ」に変わる。
〃ナアシ、ナアシは馬籠のことば〃といわれるほど馬籠独特のことばである。ナアシはナモシの美濃ことばの変化したものといわれているが、軟らかい響きがある「・・です」の丁寧語である。語尾を上げる場合と下げる場合の使い分けが難しい。仲間同士ではナアシの代わりに「ノイ」が遣われる。
馬籠では語尾に「イ」をつける場合が多い。たとえば「そうかイ」(そうですか)、「行ったぞイ」(行きましたよ)。 ナンショコトバは大人の専用語でこどもは使わない。「お休みナンショ」、「ごめんナンショ」など「・・なさい」の丁寧語だが、このことばは長野県・飯田方面から流入してきたものと思う。
|
| 1、食物編(食べ物に関係する馬籠のことば) Aボタンで正解が表示されます |
|
| 2、生き物編(動物・昆虫に関係する馬籠のことば) |
|
| 3、子ども編(子どもに関係する馬籠のことば) |
このページの先頭に戻る↑ |
| 4、いろいろ編(その他馬籠のことば) |
このページの先頭に戻る↑ |
| 5、会話編(馬籠の会話ことば) |
|
| このページの先頭に戻る↑ |


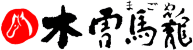
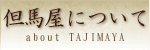

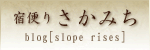
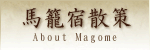
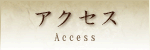
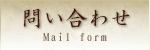
 e 自分のことを男女共にオレ。オラホは自分の家で、オラヤタは自分たち。オトウは父、オカアは母。ジジは祖父で、ババは祖母。
e 自分のことを男女共にオレ。オラホは自分の家で、オラヤタは自分たち。オトウは父、オカアは母。ジジは祖父で、ババは祖母。